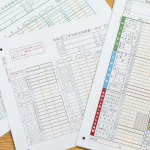紙でもらった請求書の保存方法は、電子帳簿保存法に則ったスキャナ保存、または従来通りのファイリングによる保存があります。
近年はIT化の流れもあり、電子帳簿保存法における電子保存・書類の電子化が注目を集めているため、どのようなかたちで保存すれば良いのかチェックしておきたいところです。
そこで今回は、紙でもらった請求書の保存方法について、電子帳簿保存法に則った保存要件についても整理しながら解説していきます。
紙でもらった請求書をより効率的に保存するにはどうすれば良いのか悩んでいるときは、ぜひ参考にしてください。
目次
紙でもらった請求書の保存方法は?電子帳簿保存法ではどうなるか
紙でもらった請求書を保存する場合、電子化するときは電子帳簿保存法の要件を守って正しく保存する必要があります。
また、電子化せず紙のまま保存する場合も、適切な保存方法になるように最低限の注意は必要です。
まずは、以下のポイントに沿って、紙でもらった請求書の具体的な保存方法を見ていきましょう。
- 紙のままファイリングして保存
- 電子化する場合は電子帳簿保存法に則りスキャナ保存が可能
- 電子取引書類をプリントアウトして保存するのはNG
特に電子帳簿保存法に則って電子化する場合は、保存要件の厳守が必須となるため、保存する際は十分に注意したいところです。
それぞれを詳しく解説していきます。
1. 紙のままファイリングして保存
紙でもらった請求書を保存する際の選択肢には、紙のまま保存する方法があります。
原本をそのままファイリングし、日付や書類で正しく分けた棚などに保管していきます。
近年はIT化の流れとともに電子帳簿保存法に則った電子保存が注目されていますが、紙のままの保存には、主に以下のようなメリットがあります。
- 保存方法が複雑でない
- ITになじみがない会社・従業員でも管理しやすい
- 電子化に伴う業務フローの変更がない
電子化すれば省スペース化やコスト削減などさまざまなメリットがありますが、ITになじみのない会社にとって、突然の電子保存移行は現場の混乱を招く恐れがあります。
そのため電子保存にそこまで大きな必要性を感じていなければ、紙のまま保存しても問題はないといえます。
紙のまま保存する方法は会計処理を行ったあとファイリングするのみで、やり方も複雑ではありません。
2. 電子化する場合は電子帳簿保存法に則りスキャナ保存が可能
紙でもらった請求書は、電子帳簿保存法に則り、スキャナ保存が認められています。
電子帳簿保存法では取引関係の書類の電子保存を認めており、請求書や見積書、契約書などの取引関係書類は、紙でもらった場合はスキャナ保存が可能となっています。
スキャナ保存とは、専用システムや要件を満たすスキャナー機器で原本をPCに取り込んでデータ化し、そのデータを保存することです。
なお、スキャナ保存という保存方法ではありますが、要件を満たしていれば写真撮影によって画像データ化するかたちでの電子保存も可能です。
電子帳簿保存法のスキャナ保存では、以下が要件となります。
- 入力期間の制限
- タイムスタンプの付与
- 指定解像度でスキャンしている(200pdi以上)
- カラー画像でスキャンしている
- バージョン管理
- 帳簿との相互関連性がわかる
- システム概要書の備え付け
- 見読可能装置等の備え付け
- 検索性確保
- 速やかに出力できる
見読可能装置等の備え付けとはその書類の内容を確認できる装置のことで、PCのディスプレイおよびプリンターのことを主に指しています。
上記の要件を満たせば、紙でもらった請求書は電子化が可能です。
2022年の法改正で以前よりスキャナ保存はしやすくなった
電子帳簿保存法は2022年に法改正が実施されました。
主な変更点はスキャナ保存の要件で、これにより、改正前と比べるとスキャナ保存のハードルは下がりました。
一部の変更点を挙げると、タイムスタンプの要件緩和があります。
これまでタイムスタンプは3営業日以内の不要が必須でしたが、法改正後は、おおむね最長2か月と7営業日以内に変わりました。
ほかにも検索要件が緩和されるなどさまざまな変更があったため、スキャナ保存は以前よりしやすくなりました。
そのため電子帳簿保存法に即して紙でもらった請求書をスキャナ保存する場合は、現在は意外と難しくない部分も多いため、積極的に検討するのも良いといえます。
3. 電子取引書類をプリントアウトして保存するのはNG
紙でもらった請求書の話とは異なりますが、電子取引で受け取った請求書がある場合は、プリントアウトして保存するのはNGになるため十分に注意しましょう。
電子取引の請求書は、電子帳簿保存法では電子データのまま保存する必要があります。
なお、電子取引の請求書は、以下のようなものが挙げられます。
- PDFの請求書をメールやチャットツールなどで受け取った
- 手書きだが、スキャナ取り込みによってデータ化されている請求書をメールで受け取った
- メールの文面に請求書の内容が書かれており、請求書の代わりとした
上記はすべて電子取引における取引書類にあたるため、電子取引の保存要件に則り、電子データのまま保存が必要です。
紙でもらった請求書と電子取引で受け取った請求書がそれぞれある場合は、混同しないようにくれぐれも注意してください。
フリープランならずっと無料
電子帳簿保存法対応の大容量ストレージを業界最安クラスの低価格で
セキュアな国産クラウドストレージ ibisStorage
紙でもらった請求書を電子帳簿保存法対応で保存するときのポイント

ここからは、紙でもらった請求書を電子帳簿保存法に則って保存するときの重要なポイントをまとめていきます。
事前にチェックすべきポイントは、以下のとおりです。
- スキャナ保存の要件を整理しよう
- 電子帳簿保存法対応のシステムを取り入れよう
- スキャナ保存はいつまで必要?保存期間について
では、それぞれの重要な点や注意したいことなどを整理していきましょう。
1. スキャナ保存の要件を整理しよう
紙でもらった請求書は、電子帳簿保存法においてスキャナ保存が認められています。
しかしスキャナ保存する際は、単純にPCにスキャナーで取り込めば良いというわけではないため、注意が必要です。
前述のとおりスキャナ保存には要件が定められており、保存の際は要件の把握が必須となります。
万が一要件を守らずに紙でもらった請求書を保存していた場合は、電子帳簿保存法違反になってしまいます。
2. 電子帳簿保存法対応のシステムを取り入れよう
電子帳簿保存法に則って紙でもらった請求書を電子保存する場合、スキャナ保存の要件を満たすことが不可欠となりますが、とはいえすべての要件を細かく把握することは大変に感じられることも多いでしょう。
そのため紙でもらった請求書などを電子化する場合は、電子帳簿保存法のシステムを取り入れることが望ましいです。
書類の電子化や請求書管理に活用できるシステムは、電子帳簿保存法に対応した機能が搭載されているかどうかで選びましょう。
システムを取り入れれば、多数ある請求書もスムーズにスキャナ保存できるため、管理の手間も削減できます。
3. スキャナ保存はいつまで必要?保存期間について
紙でもらった請求書を電子保存するときは、電子帳簿保存法では、法人は原則として7年の保存が求められます。
そのため少なくとも7年間は、要件をしっかり満たした状態で、自社サーバーやクラウドストレージなどで紙でもらった請求書の保存を続けましょう。
ただし保存期間については、欠損金の繰越控除を受ける法人の場合は例外となり、10年の保存が必要になるため注意が必要です。
紙でもらった請求書をスキャナ保存したあとの原本の扱い
紙でもらった請求書をスキャナ保存する場合、保存が完了したあとの原本は、破棄して問題ありません。
スキャナ保存によって紙でもらった請求書はデータ化されている状態になるため、要件を満たすことで内容はすぐ確認できる状態になっており、その時点で原本の扱いは不問となります。
ただし破棄する場合は、情報漏洩防止のために必ずシュレッダーを使用するなど、基本的な破棄ルールは守るようにしましょう。
また、紙でもらった請求書がいくつもあるときは、電子保存が完了していない書類と混同しないようにくれぐれも注意してください。
フリープランならずっと無料
電子帳簿保存法対応の大容量ストレージを業界最安クラスの低価格で
セキュアな国産クラウドストレージ ibisStorage
紙でもらった請求書を電子帳簿保存法に即して保存するメリット

電子帳簿保存法では、紙でもらった請求書もスキャナ保存で電子化できるため、実際に電子化すればさまざまなメリットを感じられます。
「そろそろ自社も書類電子化に向けて動くべき?」と迷ったときは、請求書を電子保存するメリットを整理しておきましょう。
主なメリットは、以下が挙げられます。
- 保存コストの削減
- 保管スペースの削減
- クラウドストレージに保存すれば社外からでも閲覧可能
- 有事の際も紛失・劣化のリスクを抑えられる
電子帳簿保存法の要件を守ってスキャナ保存すれば、上記のように多くのメリットが望めるため、業務効率化やコスト削減につながる可能性があります。
では、メリットを一つひとつ見ていきましょう。
1. 保存コストの削減
紙でもらった請求書を電子保存に切り替えれば、今まで必要だった保存に関するコストを削減できます。
わかりやすくいうとペーパーレス化につながるため、紙代やインク代、ファイル代などをまとめてカットできることが利点です。また過去の書類の取り出しや、社内での情報共有のコスト、書類の整理のコストも下がります。
保存コストが安く収まれば、余ったコストをサービスや商品に還元できる可能性があり、最終的にサービスの質が上がることで利益向上が見込めるでしょう。
2.保管スペースの削減
紙でもらった請求書を電子保存にすると、保管スペースの削減にもつながります。
紙での保存は物理的にスペースを取るため、たくさんのファイルを保管するための棚や倉庫が必要になります。
一方でデータ化された状態の紙でもらった請求書は、一つひとつがスキャナ保存によってデータになっているため、何百枚と保存してもまったくスペースを取りません。
保管スペースに余裕ができれば、業務のために有効活用できるでしょう。
また、不要なスペースが生まれれば広いオフィスを借りる必要もなくなり、賃料の削減にもつながります。
3. クラウドストレージに保存すれば社外からでも閲覧可能
紙でもらった請求書は、電子保存にあたって保存先をクラウドストレージにすれば、社外からでも閲覧できるようになります。
そのため場所を問わず業務を進めやすくなり、書類管理や請求の仕事が効率化する可能性が出てくるでしょう。
クラウドストレージは、オンライン環境があればどこからでも閲覧できることが大きなメリットです。
電子帳簿保存法対応の請求システムを取り入れれば、請求フローとあわせて業務効率化の効果にも期待できます。
4. 有事の際も紛失・劣化のリスクを抑えられる
紙でもらった請求書を電子化して保存すれば、有事の際も紛失・劣化のリスクを最小限にとどめられる可能性があります。
特に保存先がクラウドストレージの場合は、地震や洪水、火災などで紛失・劣化が起こって社内サーバーが被害を受けたときでも、紛失・劣化することがありません。
クラウドストレージにデータがあるため、有事の際も通常どおりの保存状態を守れるということです。
災害などの有事に備え、事業を継続させていく対策を実施することは、企業にとって常に求められる取り組みになります。
よくある質問
最後に、紙でもらった請求書についてよくある質問を紹介していきます。
- 紙でもらった請求書をスキャナ保存するときの保存先は?
- 電子帳簿保存法に違反するとどうなる?
それぞれの回答を見ていきましょう。
1. 紙でもらった請求書をスキャナ保存するときの保存先は?
紙でもらった請求書は、電子帳簿保存法に則ってスキャナ保存する場合、保存先については特に決まりはありません。
選択肢としては、会社のサーバー内、PCのハードディスク内、クラウドストレージ、SDカードなどの外部メディアが主に挙げられます。
社外からでも閲覧できるという意味ではクラウドストレージがおすすめですが、クラウドに保存する際はセキュリティ対策を徹底しましょう。
2.電子帳簿保存法に違反するとどうなる?
電子帳簿保存法に違反した場合、以下のような罰則が設けられています。
- 青色申告の取り消し
- 追徴課税
- 会社法に則った過料の支払い
これらの罰則の対象になる恐れがあるため、電子帳簿保存法の要件はしっかりと確認し、誤りのないように紙でもらった請求書を保存しましょう。
まとめ
紙でもらった請求書は、電子帳簿保存法に則り、スキャナ保存が可能になります。
そのため紙でもらった請求書を効率良く保存したいときは、従来のファイリングでの保存ではなく、スキャナ保存での電子化も検討してみましょう。
ただし電子帳簿保存法に対応する際は、保存要件を必ず満たす必要があります。
具体的な要件や保存方法はしっかりとチェックし、適切なシステムも導入したうえで、トラブルなく紙でもらった請求書の電子保存を実行しましょう。