
2024年1月に電子帳簿保存法が完全義務化され、請求書控えを含む国税関係帳簿書類の電子データ保存が可能となりました。しかし、電子データ保存するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
また、請求書や請求書控えは一定期間、定められた保存方法による保存が義務付けられています。
ここまで聞いて、「電子帳簿保存法についてよく知らない…」と不安になってしまった方がいるのではないでしょうか。
この記事では、「電子帳簿保存法に対応した請求書・請求書控えの保存方法」について解説していきます。また、事業形態別の保存期間の違いについても一緒に説明します。
複雑な内容で、困惑する方も多い電子帳簿保存法やインボイス制度に対応した請求書管理を実現させるためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
【電子帳簿保存法】請求書の控えの保存方法
2022年1月の電子帳簿保存法の改正 ※ によって、請求書控えを含む国税関係帳簿書類の、電子データ保存が可能になりました。完全義務化は2024年1月からです。
請求書や請求書控えの発行は任意であるため、発行せずに取引することができます。しかし、発行した場合は一定期間、定められた方法で保存しなければなりません。
ここでは請求書控えの保存方法を発行方法別に解説していきます。保存方法を誤ると、重いペナルティが科されるケースもありますので、しっかり確認していきましょう。
※ 参照:電子帳簿保存法|国税庁
1. 電子データの請求書の控えの場合
電子取引された請求書控えは電子データのままでの保存が義務付けられています。
電子取引とは、電子メールやクラウドといった電子データでのやり取りを指します。
この電子取引された請求書控えを、紙で印刷して保存することは認められていません。
しかし、以下の要件を満たして電子データ保存が行われているのであれば、社内管理用として請求書控えを紙で印刷して保存することは認められています。※
- 真実性の確保
- 可視性の確保
※ 引用元:国税庁
電子取引の保存要件
| 真実性の要件 | 以下の措置のいずれかを行うこと
|
|---|---|
| 可視性の要件 |
|
真実性の要件については、想定しているのは税務署が税務調査で会社に訪問したときに、指定された証憑書類をみせるよう求めがあったときに、変更や改ざんがないのか、または変更があるならいつ変更したのか、また受領してすぐにクラウドストレージ等に保存したのか、等が確認できる必要があるということと思われます。
税務署調査の直前に証憑書類をクラウドストレージに保存等では改ざんを疑われるので、証憑書類の受領から1ヶ月以内にはクラウドストレージに保存等をするルールにしましょう。
可視性の要件については、想定しているのは税務署が税務調査で会社に訪問したときに、指定された証憑書類をディスプレイで表示してください、または、プリンタで印刷してくださいという求めに対してスピーディに対応できるようにしてください。ということと思われます。
そのため整理された状態でファイルを管理したり、検索機能でスピーディに証憑書類を見つけられるようにしたりしてくださいということです。
また、保存の義務は請求書控えの発行者・受領者双方に適用される点に注意が必要です。
2. 紙の請求書の控えの場合
印刷された紙の請求書控えの場合、そのまま紙で保存して問題ありません。
あくまでも任意ではありますが、スキャンによる電子データでの保存も可能です。電子データ保存するためには、前述した「真実性の確保」「可視性の確保」の要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存法が制定されてからしばらくは、電子データ保存の要件が厳しかったことから、紙での保存を電子データ保存に切り替える企業はあまり見られませんでした。しかし、2022年の法改正を受け、電子データ保存の要件が緩和され、また、2024年に完全義務化されたことで多くの企業で電子データ保存への切り替えが進んでいます。
また、紙での保存であっても電子データと同様、保存の義務は請求書控えの発行者・受領者双方に適用される点に注意が必要です。
フリープランならずっと無料
電子帳簿保存法対応の大容量ストレージを業界最安クラスの低価格で
セキュアな国産クラウドストレージ ibisStorage
請求書の控えは電子データがおすすめな理由
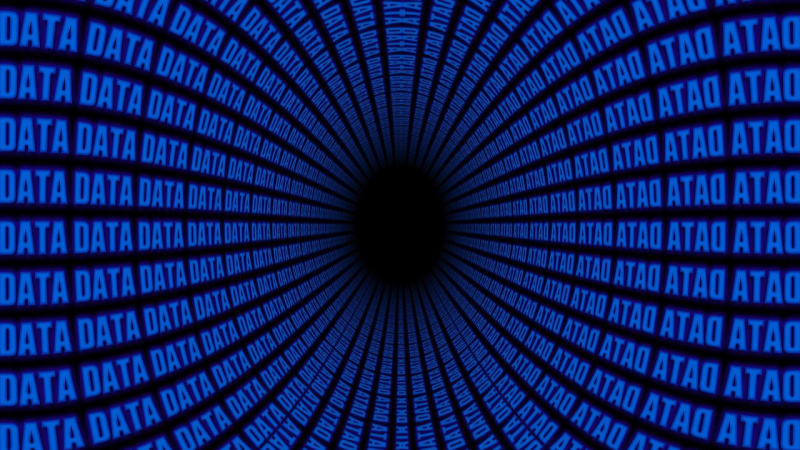
ここまでで、電子帳簿保存法の改正によって、請求書控えの電子データ保存が可能になったことを解説しました。
多くの企業で請求書控えを含む、国税関係帳簿書類の電子データ保存への切り替えが進んでいます。
なぜ要件を満たす必要がある電子データ保存に切り替える企業が増えているのでしょうか。ここでは、請求書控えを電子データ化するメリット・おすすめの理由について解説していきます。
1. 紙より管理が簡単で楽になる
電子データは紙よりも管理が簡単で、手間がかかりにくいといったメリットがあります。
発行された請求書控えは、定められた保存方法で保存しなくてはなりません。
慣れているとなかなか気付きにくいですが、紙で管理する場合、以下のような手間が生じています。
- 印刷
- ファイリング
- 仕分け
- 人の手による資料探し
また、書類の量が膨大な場合は、管理スペースの確保や印刷にかかる用紙代・インク代など大きなコストもかかっているでしょう。
こういった手間やコストが、電子データ保存であれば一切かかりません。データはパソコンさえあれば管理できます。資料もファイル名の検索ですぐに見つかります。
経理担当の方たちの負担の軽減や、通常業務の効率化にも繋がるでしょう。
2. インボイス制度の負担が減る
電子データ保存はインボイス制度による負担を軽減することができます。
2023年10月1日から開始されたインボイス制度 ※ によって、適格請求書発行事業者は適格請求書控えの発行・保存が義務化されました。
適格請求書は従来の請求書よりも記載事項などが増えたため、管理に手間がかかります。たとえば、登録番号の照合などに関しては、紙での管理は非常に負担が大きくなります。
そこで、電子データを利用することで、データ管理を楽にできるというわけです。電子データによって、そもそもの制度自体が複雑なインボイス制度にも対応しやすくなるでしょう。
※ 参照:適格請求書等保存方式の概要|国税庁
3. 企業間の取引が効率化できる
請求書ならびに請求書控えの電子データ化は、企業間の取引を効率化させます。
印刷した紙で書類のやり取りを行っている場合、以下のような工程を踏むため、タイムラグが起こります。
- 印刷
- 封入
- 郵送
書類に不備があった場合は、修正が加わりさらに倍の時間がかかるでしょう。
しかし電子データであれば、メールやクラウドでのやり取りとなるため、タイムラグが発生しません。また、不備があってもすぐに修正・再送・確認ができます。
多くの企業と取引がある企業にとっては、電子データはスムーズなやり取りだけでなく、大きなコスト削減を実現させるでしょう。
請求書の控えの保存期間
請求書や請求書控えの発行は任意であるため、未発行のままでも取引することができます。
しかし、2023年に開始されたインボイス制度によって、適格請求書発行事業者は適格請求書控えの発行・保存が義務化されました。受領側から発行を求められた場合、発行側は必ず請求書控えを発行し、かつ保存もしなければなりません。
請求書控えは、事業形態や請求書の種類によって異なる保存期間が設けられています。
ここでは、それぞれのケース別の請求書控えの保存期間を解説していきます。
1. 法人
法人の請求書控えの保存期間は原則7年間です。
しかし、欠損金の繰越控除がある事業年度の請求書控えは10年間保存が必要になります。
年度によって繰越控除の有無が入り混じっている場合は、10年間保存しておくと安心でしょう。
また、この保存期間は確定申告書提出期限の翌日からのカウントとなる点には十分に注意が必要です。
2. 個人事業主
個人事業主の請求書控えの保存期間は原則5年間です。
しかし、課税売上高が1,000万円を超える消費税課税事業者の場合や適格請求書を発行している場合は法人と同様に7年間保存が必要になります。
また、法人同様、保存期間は確定申告書提出期限の翌日からのカウントとなる点に注意しましょう。
3. 過去副業で300万を超えた場合
前々年の副業による収入が300万円を超えている場合、5年間請求書控えを保存しなくてはなりません。
また、請求書控えだけでなく、現金・預金の取引関係書類全般が保存義務の対象となるため、領収書等の取り扱いは慎重に行いましょう。
また、請求書控えの保存期間は確定申告書提出期限の翌日からのカウントとなります。発行日や受領日ではないということを覚えておきましょう。
請求書を電子データ保存にする前のチェック事項
ここまでで請求書控えの電子データ化のメリットや保存方法について解説してきました。
大きなメリットのある電子データ保存ですが、実際に保存方法を変更する際には注意しておかなくてはならない点があります。
ここでは請求書を電子データ保存にする前のチェック事項を3つ解説していきます。
1. 請求書発行者に保存方法の変更を伝える
保存方法を電子データに切り替える場合は、請求書の発行側にその旨を伝えておきましょう。
電子保存に変更すると、紙の請求書は不要になります。その旨を発行側にも伝えておくことで、印刷や郵送の手間がなくなるため、その分のコスト削減が可能となります。
余分な請求書の受け取りを避けるためにも、発行者への連絡は大切です。
2. 社内で請求書の電子データの保存フローを確立する
電子データ保存に切り替える際には、社内で保存フローを確立しておくことでスムーズな移行が可能となるでしょう。
請求書の発行側がデータ保存に対応させたい場合は、請求書発行システムを導入することで効率化できます。受領側が電子帳簿保存法に対応したい場合は、電子帳簿保存対応のクラウドストレージの導入がおすすめです。
また、システムだけに依存するのではなく、社内で請求書の管理ルールを統一することで、より一層の作業の効率化に繋がります。
3. 発行側も適格請求書の保存をする
適格請求書は受領側だけでなく、発行側もその控えの保存が必要であるという点に注意しましょう。
電子データ・紙いずれの発行方法・保存方法であっても、一定期間は控えの保存が必要です。
クラウドストレージならibisStorage(アイビスストレージ)
この記事では請求書控えの保存義務や保存期間について解説してきました。
請求書控えを電子データ保存することによって、企業の取引の効率化や紙での管理にかかるコストの大きな削減が可能となります。また、2023年10月から開始されたインボイス制度の複雑な書類管理の負担も軽減できるでしょう。
ibisStorage(アイビスストレージ)は、電子帳簿保存法に対応したクラウドストレージです。ゼロトラストセキュリティによる、安心安全なデータ管理システムを業界最安クラスの低価格で提供しています。
現在、無料プランおよび30日間の無料トライアルを実施していますので、この機会にぜひibisStorageの無料プランまたは無料トライアルを利用開始しましょう。
















