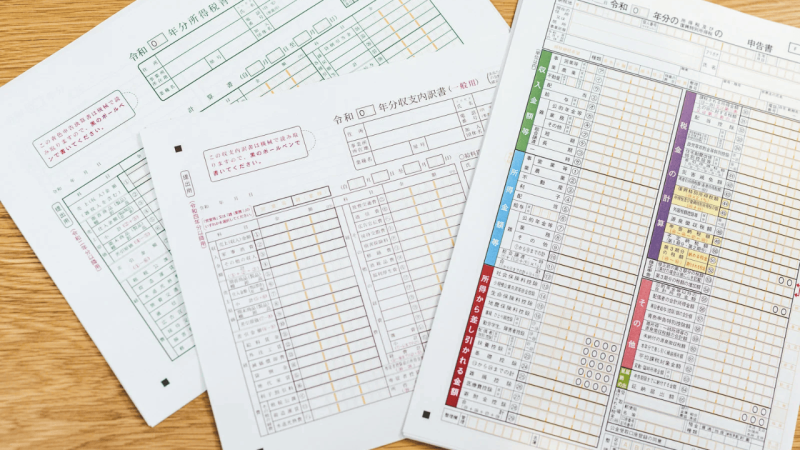
電子帳簿保存法では、注文書も保存要件を満たすかたちで電子保存が可能となります。
そのため注文書を電子化したいときは、まず電子帳簿保存法について理解を深め、必要な保存要件を整理しておきましょう。
そこで今回は、電子帳簿保存法における注文書の保存方法や保存期間、保存先などの基礎知識をまとめていきます。
あわせて電子保存する際の注意点やリスクについても触れていくため、注意点にもしっかり目を向けたうえで、安全に電子化した書類を保存・管理していきましょう。
目次
電子帳簿保存法とは何か
電子帳簿保存法は、国税・取引に関する書類の電子保存について定めている法律です。
電子保存の際に守るべき要件、電子帳簿保存法で電子保存を認めている書類などに触れているため、国税や業務上の取引に関する書類を電子的に保存する場合は、事前の理解が必須といえます。
電子帳簿保存法はもともと以前からあった法律ですが、近年のIT化により情報社会の程度はさらに発展し、業務環境では多くの企業がITシステムを取り入れたり、業務のデジタル移行を進めたりすることがますますさかんになりました。
その影響から、電子帳簿保存法は多くの場面で話題を集めるようになり、最近では2022年の法改正が記憶に新しいものです。
法改正ではさまざまな見直しがなされ、一部の保存方法の要件については緩和措置が取られたため、電子保存は以前よりも取り入れやすくなったといえます。
なお、今回紹介する注文書についても、電子帳簿保存法では複数の方法で電子保存が可能です。
注文書は取引関係書類にあたるため、注文書を受け取ったり発行したりした際は、要件を満たしたうえで、電子保存を考えてみましょう。
フリープランならずっと無料
電子帳簿保存法対応の大容量ストレージを業界最安クラスの低価格で
セキュアな国産クラウドストレージ ibisStorage
電子帳簿保存法における注文書の保存方法

電子帳簿保存法では、注文書は電子保存が可能となっています。
そのため注文書を効率良く保存したいとき、注文書の保存に関してかかっているコストを削減したいときなどは、電子帳簿保存法に則って電子保存を検討しましょう。
電子帳簿保存法における注文書の保存方法は、以下の2つのパターンが挙げられます。
- 【紙の注文書】スキャナ保存
- 【電子取引】電子データ保存
スキャナ保存と電子データ保存の違いは、注文書の受け取り・発行の形態の違いです。
紙で受け取ったのか、それともメールなど電子的なやり取りの中で受け取ったのか、それぞれ保存方法と要件は異なるため注意が必要になります。
では、電子帳簿保存法ではどのように保存するのか、詳細を整理していきましょう。
1. 【紙の注文書】スキャナ保存
紙で受け取った注文書は、電子帳簿保存法では、スキャナ保存が可能です。
スキャナ保存とは、指定の解像度などの要件を守ったうえで書類をスキャンし、データ化することで保存する方法です。
スキャナ保存で注文書を電子保存する場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 入力期間の制限
- タイムスタンプの付与
- 200dpi以上でスキャンしている
- カラーまたはグレースケールでスキャンしている
- バージョン管理
- システム概要書の備え付け
- 見読可能装置等の備え付け
- 検索性の確保
- 速やかに出力できる
注文書は、電子帳簿保存法が定める取引関係書類の中でも、「一般書類」の扱いになります。
一般書類と対になる書類として「重要書類」がありますが、重要書類とは要件が少々異なるため、混同して把握しないようにくれぐれも注意しましょう。
スキャナ保存後の原本の扱い
電子帳簿保存法では、スキャナ保存をしっかりと済ませたあとは、注文書の原本は破棄可能です。
原本もまとめて取っておく必要はなく、要件を満たしたうえでスキャナ保存ができているのであれば、原本は好きなタイミングで破棄しましょう。
ただし、注文書は個人情報やその他の重要情報が記載されている書類のため、破棄する際は必ずシュレッダーを活用することが大切です。
2. 【電子取引】電子データ保存
電子取引の注文書は、電子帳簿保存法では、電子データ保存が求められます。
電子取引とは、メールなどの連絡手段を通じて、紙ではなく電子的にやり取りしていることを指します。
電子取引の注文書に当てはまるケースは、たとえば以下のとおりです。
- メールやチャットツールなどで添付してもらって受け取った注文書
- メールに直接注文内容を書いてもらい、メールの文面を代わりに注文書とした
電子的な手段でやり取りした注文書を電子データのまま保存する際は、以下の要件を満たすことが必須となります。
- 改ざん防止措置
- 見読可能装置の備付け
- 検索性の確保
改ざん防止装置としてできることは、たとえばタイムスタンプ付与や訂正削除履歴機能付きのクラウドストレージに保管することなどが挙げられます。
電子帳簿保存法では、電子データのまま保存する際はそこまで要件が多くないことが特徴です。
電子取引の注文書は印刷した状態での保存はNG
電子取引の注文書は、電子帳簿保存法に則り、電子データのまま保存することが必要です。
そのため、電子取引の注文書を印刷した状態で保管することはNGとなります。
印刷して保管すれば、一見すると正しく保管しているようにも思えますが、電子取引の注文書は電子データのまま保存する必要があります。
注文書はいつまで保存が必要?
注文書の保存期間は、以下のように年数が定められています。
- 法人:原則として7年保存
- 個人事業主:原則として5年保存
ただし、法人のみ、欠損金の繰越控除を受ける場合は、保存期間は10年となります。
「個人は5年、法人は基本的に7年、欠損金の繰越控除がある場合のみ10年」という認識でとらえておきましょう。
フリープランならずっと無料
電子帳簿保存法対応の大容量ストレージを業界最安クラスの低価格で
セキュアな国産クラウドストレージ ibisStorage
電子帳簿保存法における注文書の適切な保存先

電子帳簿保存法では、注文書を電子保存する場所については特に定められていません。
そのため保存先についてはある程度自由に選ぶことができ、要件を満たして電子保存されている状態であれば、問題はないとされています。
保存先については、具体的には以下のような選択肢を検討できるでしょう。
- クラウドストレージ
- 自社サーバー・NAS・ハードディスク
- CD・DVDなどのメディア
それぞれの特徴やメリット、保存時の注意点などを以下から整理していきます。
1. クラウドストレージ
まずは、クラウドストレージを活用して電子保存する方法があります。
注文書のように多くの枚数を保存する必要のある書類は、容量を圧迫しないためにも、クラウドストレージを活用して保存したほうが業務効率アップにもつながるでしょう。
多くのデータを保存している企業であれば、クラウドストレージは容量無制限になっている場合もよくあるため、なおさら容量を気にせず安心感を持って保存できます。
クラウドストレージに電子保存すれば、社外からでも必要に応じて参照・管理できる点がメリットです。
クラウドという環境ゆえにセキュリティのリスクはやや上がってしまうため、高水準のセキュリティ対策は大前提として必要になりますが、保存しておけば利便性が高いことは間違いありません。
2. 自社サーバー・NAS・ハードディスク
電子帳簿保存法に対応して注文書を電子保存する場合は、自社サーバーやNAS、ハードディスクを選ぶこともおすすめです。
自社サーバーやNAS、ハードディスクの場合のセキュリティですが、社内に置いているためある程度は安心できますが、昨今のランサムウェア攻撃の被害ではルーターやVPNの脆弱性をついたものや、マルウェアに感染して自社サーバーやNASにアクセスされるという被害が多く報告されています。
社内においてあるから安心ということで油断をすると危険です。正しくアクセス権を設定したり、VPN機器の脆弱性パッチの更新、自社サーバーのOSの更新等の正しい運用が必要になります。
自社サーバーやNAS、ハードディスクは社外からではアクセスできませんが、「過去の注文書を社外にいる状態で閲覧することはほぼないから大丈夫」というときは、自社サーバーやNAS、ハードディスクに保存しても不便さを感じることはないでしょう。
ただし社内サーバーやNAS、PCのハードディスク等は、サーバーの故障、PCの故障でデータが消失するリスクがあります。また、復旧作業、ストレージ容量の増設作業、データ移行作業、バックアップ作業等の運用コストがかかることがデメリットです。
3. CD・DVDなどのメディア
電子帳簿保存法に即して注文書を電子保存する際は、CDやDVDなどの外部メディアを頬損場所にすることも良いでしょう。
外部メディアは、ほかにSDカードやUSBメモリ、外付けタイプのハードディスクが挙げられます。
外部メディアもオフライン環境での利用が基本のため、通信を狙った脅威にさらされにくいことがメリットです。
さらに外部メディアは必要に応じて持ち運べるため、クラウドストレージほどではないとはいえ、社外からでも閲覧できる可能性がある点は強みの一つになるでしょう。
しかし外部メディア自体の保存スペースが必要なことや、無断での持ち出しなどがないように厳重に管理する必要があることは、電子保存するうえで難点になります。SDカード、USBメモリ、外付けハードディスクの故障や紛失などの非常に高いリスクを伴います。
メディア一つにつき保存容量が限られることも、注意が必要です。
電子帳簿保存法対応で注文書を電子保存する際の注意点
ここからは、電子帳簿保存法に則り、注文書を電子保存するときに注意したいポイントを整理していきましょう。
電子帳簿保存法では、スキャナ保存または電子データ保存で注文書の電子保存が可能ですが、実際に電子保存を始める際はさまざまな点には注意が必要です。
主な注意点は以下のとおりです。
- システムを導入して正しく保存しよう
- クラウドストレージのセキュリティ対策は万全に
- 注文書控えも電子保存が可能
具体的に何に注意が必要なのか、詳細を解説していきます。
1. システムを導入して正しく保存しよう
電子帳簿保存法に即して、注文書を含む書類を電子保存するときは、原則として電子化のためのシステムが必要になります。
システムがあると、要件を意識して正しく保存できること、作業効率化の面でも利便性を感じられることなどのメリットを感じられるでしょう。
注文書の場合、電子化にあたって積極的に取り入れたいものに、受発注システムなどのクラウドサービスがあります。
電子帳簿保存法に対応しているシステムであれば、受け取った注文書の保存要件を押さえたうえで電子保存できるため、複雑な保存要件を把握するうえで良いサポートになるでしょう。またそのような機能がなくても注文書をファイルとして保存できればクラウドストレージへ保存することもできます。
紙の注文書をスキャナ保存する際も、電子帳簿保存法対応のクラウドストレージなどのサービスを導入しておいたほうが安心です。
そのため注文書の電子化・電子保存を進める際は、システム導入もほぼセットになることを理解しておきましょう。
2. クラウドストレージのセキュリティ対策は万全に
クラウドに注文書を電子保存する場合は、セキュリティ対策を万全にする必要があります。
たとえばセキュリティ対策に不安要素がある状態だと、情報漏洩などのインシデントにつながる恐れがあるためです。
クラウドストレージでは、常にネットに接続した環境でファイルのやり取りをするため、電波傍受などで大事なデータを盗み見される可能性があります。
多くの社員がクラウドストレージのアカウントを持っている場合、万が一IDとパスワードが流出すれば、不正にログインされてしまうこともあり得ます。
情報漏洩のトラブルを起こさないためには、以下のような高水準のセキュリティ機能を持つクラウドストレージの活用が重要です。
- 通信の暗号化
- 管理者設定によるアクセス権限のコントロール
- 多要素認証や端末認証
- 不審な動きの検知
- ログ記録
このようにセキュリティ性に優れた機能がそろっているクラウドストレージであれば、電子保存もしやすくなるでしょう。
電子帳簿保存法に則って電子保存する書類は、国税や取引に関する大事な書類ばかりです。
情報漏洩を起こさないように考慮し、セキュリティ対策には常に気を配りましょう。
3. 注文書控えも電子保存が可能
電子帳簿保存法では、自己発行した注文書、つまりは注文書控えも電子保存できる書類の対象になります。
そのため業務効率化を目指す場合は、受け取った注文書だけでなく自社で発行した注文書の控えも、電子保存することで管理しやすくすると良いでしょう。
注文書控えも同様に取引関係書類となるため、保存方法はスキャナ保存または電子データ保存のどちらかになります。
まとめ
電子帳簿保存法では、注文書も電子保存が可能になります。
そもそも注文書は、法人の場合は原則7年の保存義務があるため、長期的に保存するのであれば管理しやすい電子保存を選びたいところです。
保存方法はスキャナ保存または電子データ保存のいずれかになりますが、両方とも共通していえることは、電子帳簿保存法の保存要件をそれぞれしっかり守ることです。
必要に応じて新しくシステムを導入することも検討したうえで、電子保存することで、受発注業務や書類の管理業務を効率化させていきましょう。
















